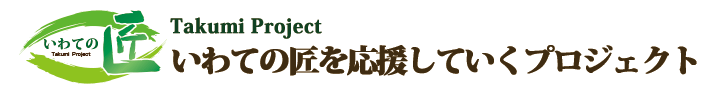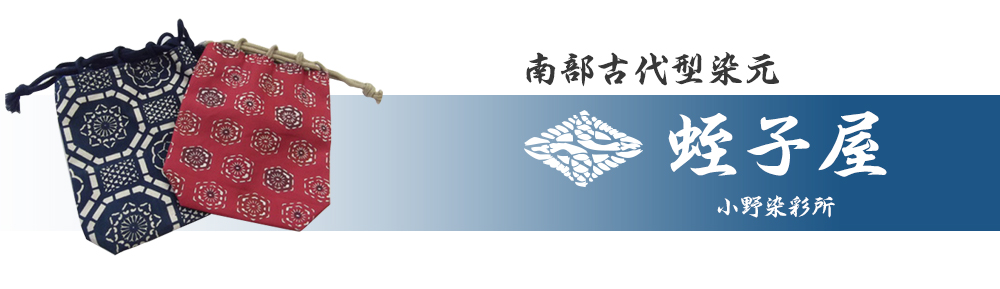南部古代型染とは

南部古代型染は、古く南部藩時代に武家の間に用いられた衣類等の図柄を今日に生かしたものです。昔は裃、袴、小袖に使用されたものでした。
私どもの家業は藩政時代からこの型染に専心し、他からの影響をあまり受けることなく、今に続いております染師。 製品の完成度に留意すると共に、時代への適合も心がけて制作しています。伝統的なすくも藍、ふすま、木灰の醗酵建てによる藍色の躍動が藍染めの 魅力であり、昔ながらの染法を今も守り続け、魅力を放っています。

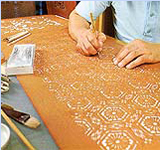
型彫りは、基本となるデザインの型紙を切り抜いて模様を作ることから始まります。型彫りは、型染の最も重要な技法の一つで、 長い間の修練と根気を要します。型彫りには次の[突彫り] [錐彫り] [道具彫り] [引彫り]による四つの技法がそれぞれの内容によって用いられます。

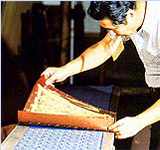
糊置きは予め精錬(織糊、糸の油分を除く)した乾燥した生地に型紙をのせて上からヘラで糊を生地に連続して印捺するものです。 その際用いる糊を防染糊と云います


染めは材料のすくも藍、ふすま、木灰にて醗酵によるものです。糊置きと藍染の合体により、好みの濃度に染め上げられてゆきます。 洗う毎に色彩の鮮やかさを感じさせます。絹、木綿、麻の染色に供します。
取扱い商品

南部古代型染は型紙を基本にして布地の上に糊置きをして染め抜く手法でありますが、この様にして印捺された布地は着物は 勿論のこと、ノレン、帯、テーブルセンター、袋、小物類と各方面に応用されており、ご贈答品、引き出物にも最適です。 各々の製品には伝統的工芸品の持つ優雅さ、野生味と、豪快な動きが見られます。
私どもは染色全般についてお客様のご予算に応じ対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。
代表的な柄
種類は数百種類に及びますが、その中でも代表的な物を3点ご紹介します。

向鶴(むかいづる)
南部公の紋章、向鶴を菱文に文様化したものである。この菱鶴の形状は、南部古代型独特のものです。
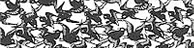
千羽千鳥(せんばちどり)
甲州南部郷の将、南部義光とともに三戸に渡った染師蛭子屋三右エ門は、海岸に群れ飛ぶ千鳥の美しさにみとれて、 その模様を型に彫ったものという。南部古代型の独特な模様です。

南部萩(なんぶはぎ)
南部古代型の中でも最古の模様と思われる。乱れ彫りの中に、線の流れの美しさがみられます。
お問い合わせこちら
| 名称 | 南部古代型染元 蛭子屋 (有)小野染彩所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒020-0063 岩手県盛岡市材木町10-16 |
| TEL | 019-652-4116 |
| FAX | 019-652-4105 |
| info@katazome.jp | |
| 南部古代型染 | https://www.katazome.jp |
| 営業日 | 日曜日定休日のほか 平日、祝日に不定期臨時休業の場合がございます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが お確かめの上ご来店いただきますようお願い申し上げます。 |
| 営業日 | 10:00~17:00 |